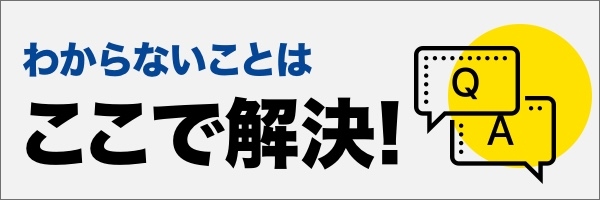✕ 閉じる
ものづくり
2024年02月02日
ジオラマ作家・情景師アラーキー「リアリティを生み出すのは知識と技術、そして妄想」

昭和の街並みや「バットマン」のゴッサムシティなど、SNSでも話題となった “リアルすぎるジオラマ”を制作している情景師アラーキーさん。大手電機メーカーでプロダクトデザイナーとして働きながら、子ども時代からの趣味であるジオラマ制作を続け、45歳でフリーランスのジオラマ作家として独立したという。ジオラマをつくりはじめた背景や、リアルさを生み出す細部のこだわりなどを聞いた。
(取材・文 菅原さくら/写真 タケシタトモヒロ)
スキルのほとんどは、中学生までに身についたもの
物心ついたときから手を動かすことが好きだったアラーキーさん。3歳くらいから模型や工作、箱庭といったものづくりを始めていたという。

「興味があるのは“リアルなものを作ること”だけ。特撮ドラマの全盛期だったこともあり、背景セットやかっこいいマシンなどにも憧れを抱いていました。だけど、建物も乗り物も、自分ではそこまでリアルに作れなかったんですよね。幼いころから何かを作る遊びばかりしながら、もっとスキルが身についたらいいのになぁ、と思い続ける日々でした」
ものづくりへの関心が強まっていった理由のひとつは、本格的な道具の存在だ。小さなころから肥後守(小刀)や接着剤など、幼児用ではない本物を与えられてきた。
「本格的な道具を持つと『これがあれば何でもできる』って、気持ちがぐっと上がるんです。セメダインの工作用接着剤もそのひとつでしたね。ふつうの糊と違って空き缶やプラスチックなどもくっつけられるから、作れるものの幅がずいぶん広がった。少年時代はプラモデルに熱中して、本物そっくりの車をたくさん作りました」

「いまもセメダインのエポキシパテ木部用を愛用。あっという間に固まるから、待たずにサクサク作業を進められるという」
ジオラマ制作をはじめたのは、中学生のとき。一般向けの模型雑誌を目にして衝撃を受けたのがきっかけだ。聞いたこともないような道具や材料を使って作られた精巧な模型たちは、少年アラーキーの心を撃ち抜いた。
「いまはまだお小遣いも少ないし、中学時代に住んでいた北九州では買えないものがたくさんある。だけどいつか大きくなって東京に行ったらこの店でこの道具を買おうって、雑誌にたくさんメモを取っていましたね。その一方で、作ってみたいと思うものにはとにかくなんでもトライしてみました。たとえばプラモデルひとつ取っても、説明書どおりに作って塗装するだけでは物足りない。製品では再現されていない本物の部分を作り込むために、あえて穴を開けたり厚みを変えたり……戦艦大和のプラモデルでは、何本ものケーブル線を作って艦橋から張りめぐらせたこともありました。そのうち、プラ板ですべてのパーツから自作するフルスクラッチにも挑戦。模型雑誌に書かれていた技術をすべて身につけたくて、本当にいろんなチャレンジをしたと思います。いまの僕のスキルのほとんどは、この中学生時代に培われたものだと思う」
悩みに悩んだ、フリーランスのジオラマ作家への転身
アラーキー少年のジオラマが模型雑誌のコンテストで入選をするようになるまで、さほど時間はかからなかった。ところが、ときは平成初期。若者たちはスキーやスキューバ、音楽といったさまざまな趣味にのめり込んでいたが、模型やジオラマといったサブカルチャーには、まだ日が当たっていなかった。
「プラモデルやジオラマが趣味だと言うとモテないから、表立ってはやらず、こっそり続ける“裏の趣味”にしていたんです(笑)。レコードやファッションも好きだったし、限りあるお小遣いをどう配分するかを考えて動いているうちに、プラモデルづくりからは少し距離があいた時期かもしれません。でも、やっぱり興味はあったので、大学で工業デザインを学び、卒業後は電機メーカーのプロダクトデザイナーになりました。図面を書いたり、手作業でモックアップを作ったりしているうちは楽しかったんですが、だんだん業務のデジタル化が進んで……一日じゅうパソコンに向かって仕事をしている自分に気づいたとき、自分は本当にこういうことがしたかったんだっけ? と悩んだ。せっかく小さいころから鍛えた手作業のスキルも鈍っていく気がして、まずは趣味のジオラマ制作を本格的に再開しました」
プロダクトデザインの仕事と趣味のジオラマ制作を続けていたアラーキーさんに、転機が訪れたのは30代なかばのこと。ずっと読んできた憧れの模型雑誌から、記事執筆の声がかかったのだ。ただし、サラリーマンをしながら本名で記事を書くわけにはいかない。そこで、現在に至るまで名乗っている「情景師アラーキー」というジオラマ作家ネームが生まれた。
「表向きはプロダクトデザイナーの荒木智で、after5にジオラマ制作を楽しむ別人格が情景師アラーキー。この棲み分けはすごくいいなと思いました」と、当時を振り返って微笑む。

しかし、これほど完成度の高いジオラマが、世の中に見つからないはずもない。いつか作品集が出せたらと、こまめにSNSに流してきた作品画像が大きくバズり、さまざまなメディアの取材が舞い込んだ。BBCの「ディスカバリーチャンネル」から特集取材の打診もあったのもこのころだ。
「サラリーマンとジオラマの二足の草鞋では、どうしても活動が制限されてしまいます。でも、当時はまだ『ジオラマ作家』なんて肩書きは世の中に存在していなかったし、ジオラマでどうやって稼いだらいいかもよくわからない。しばらくは、好きなことで食べていきたい気持ちと不安で悶々としていましたね。そんなときに、大きなピンチとチャンスが同時に訪れたんです。ピンチは、本業で花形の部署に異動したらものすごく忙しくなって、趣味の時間が全然取れなくなってきたこと。チャンスは、ずっと出したかった作品集を出版してから、ジオラマ制作の依頼が殺到したことです。二者択一の状況に陥って、逆に決心がつき、44歳でフリーランスのジオラマ作家に転身しました」
日々のたゆまぬ勉強が、超精密なジオラマを生む
アラーキーさんのジオラマの特長は、その緻密さにある。取材で訪れたアトリエには、ひときわ目を引く作例が飾ってあった。昭和の駄菓子屋だ。

「作家として仕事をしていると、当たり前なのですが、作ったジオラマが手元を離れていくんです。頼まれて制作しているのだから納品しなきゃいけないのだけれど、作っているうちに愛着がわいて、いつも手放すのが惜しくなる。そこで数年前、そのときの自分の技術をすべてつぎ込んだ最高傑作を生み出して、ずっと手元に置いておこうと思って作ったのが、この駄菓子屋です」
まずこだわったのは、家屋の骨組み。建築のプロが見ても「リアルだ」と感じるような作品にしたくて、日本の木造建築について勉強することから着手した。柱や屋根、板、畳などのサイズや質感など、すべてにおいてリアリティを追求している。「骨組みが出来上がって塗装に入る段階では、よき日を選んで棟上げ式もやりました」と、おちゃめに笑う。

その店先に並ぶのは、本物と見紛うような駄菓子や吊るし玩具、プラモデルだ。ほとんどがペーパークラフトで、本物を撮影して1/24サイズに縮小し、紙を半分の薄さに削いだあと、組み立てたり折り目を付けたりして作っていった。ビニール袋に入った商品の質感を出すには、接着剤が必須。紙の表面につまようじで「スーパーXG」をのせ、表面張力で盛り上がった形のまま乾かすと、商品が透明の袋に入っているように見える。

建物と小物がどれだけ緻密に作られていても、それだけでは世界観を徹底しきれない。仕上がったばかりのパーツは真新しく、時間の経過を感じさせないからだ。そこでアラーキーさんは、看板のサビやブロック塀の雨だれ、板塀の木目などを、手作業で描きくわえていく。
「店前のアスファルトも、どうやって再現したらいいんだろうと悩みました。いろいろなシミュレーションをして、最終的に選んだのは本物のアスファルトと同じ手法です。石膏に黒い塗料を混ぜて着色したものに鉄道模型用の細かい砂利を入れて、ベースに流し込む。それから、木製のミニチュアトンボを使って、地面をならします。ドライヤーで乾燥させたら、いい具合にクラックが入りました。それから、カッターでもう少し表面をガリガリにして……」
「本物みたいでしょう? このあたりは追加で下水工事なんかがあったのかもしれませんね」とアスファルトをなでる姿から、アラーキーさんが本当にこのジオラマを愛おしく感じていることが伝わってくる。

「こうしたリアリティを追求するには、日々勉強しかありません。知識とスキルで正確なものを作ったら、そのうえに妄想を重ねる。僕のジオラマがリアルだと思っていただけるなら、妄想に支えられた“生活臭”があるからだと思います。たとえば角のブロック塀に、立ちション防止の鳥居が描かれているでしょう。きっとこの近くに居酒屋でもあって、しょっちゅう迷惑をこうむるんでしょうね。でも、鳥居をわざわざ描くってことは、ここの家にはちょっと神経質な人が住んでいるのかもしれません。それからこの角はたぶん道幅が狭くて、しょっちゅう車がこすれるから、こういう傷がつくのかも。……なんてバックボーンをいろいろ妄想して盛り込んでいくことが、リアリティの再現に直結すると感じています」


ジオラマの可能性は無限大
ジオラマを専業にして、今年で9年目。みずから仕事を開拓していかなければならないプレッシャーはあっても、毎日は楽しい。制作やインプットに当てる時間が増えたことも大きな喜びだ。

「ずっと年休をとり続けて、好きなことばっかりしているような気分なんです。『そろそろ仕事に復帰しないと、社会人に戻れないんじゃないか?』と思ってしまうくらい、ジオラマ制作は仕事という感じがしません。オファーをいただくたびに『そんなに面白そうなもの、僕がつくっていいの?』と思うし、一つとして同じ依頼はない。そのぶん毎回ゼロから勉強しなければならないことがたくさんあるけれど、その学びも楽しいです」
とくに印象的だった事例を尋ねると「独立2年目に、福島県相馬郡にある新地町役場からいただいた震災復興のお仕事です」という答えが返ってきた。津波で失われた町の地図をつくり、お気に入りの場所や思い出のスポットをマッピングすることが、被災者のメンタルケアに役立つという。そこで、被災した住民たちと一緒に町のジオラマを制作するべく、アラーキーさんに声がかかった。
「町のジオラマを僕一人で作るだけならともかく、参加者全員で作るとなると、これはとても大変です。でも、だからこそ会社員と両立していてはできない難しい仕事。いま僕がやるべきことだと使命感を感じて、お受けしました。
被災した方々が作りたいと言ったのは、町のシンボルだった新地駅でした。かわいらしい木造の駅舎だったのですが、津波で流されてしまったのです。古い駅だったためJRに問い合わせても駅舎の図面が残っておらず、同年代の駅舎写真をヒントに図面を書き起こしました。それから、実際に手を動かすみなさんに『ジオラマとは何ぞや?』を知っていただくためにミニジオラマ展を開いて、ゴールのイメージを共有。作業しやすいキットを用意し、5歳から86歳までの参加者が全員で楽しみながら制作できるように、さまざまな工夫をしましたね」
ジオラマの仕事ってこんなにバリエーションがあるんだ、と、アラーキーさんは自分の選んだ道の広がりを感じたという。以来、いくつもの刺激的な仕事に携わってきた。最後に、これから挑戦していきたいことを尋ねてみる。
「僕はどこまでいっても手作りが好きだし、手間をかけた作業は人を驚愕させてくれます。ジオラマを生み出すにはさまざまな専用の道具があるけれど、極端にいえば、カッターと定規と接着剤さえあればなんだってできるんです。だから、どこまでアナログでできるかには、これからも勝負してみたいと思っています。とはいえ、効率的にものづくりをしていくうえでは、3Dプリンターみたいな最新のツールも避けて通れません。うまくバランスを取りながら、手を動かし続けていきたいですね」

ライター:菅原さくら
フリーランスのライター/編集者/雑誌「走るひと」チーフなど。1987年の早生まれ。北海道出身の滋賀県育ち。早稲田大学教育学部国語国文学科卒。
インタビューが得意で、生き方・パートナーシップ・表現・ジェンダーなどに興味があります。メディア、広告、採用などお仕事のジャンルはさまざま。
6歳3歳の兄弟育児中。高校生のときからずっと聴いているのはBUMP OF CHICKENです。
https://www.sugawara-sakura.com/
関連記事
タグ一覧