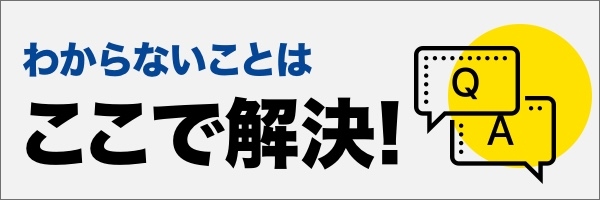✕ 閉じる
ものづくり
2021年08月31日
福を呼び込み、幸を届ける。分業制で、職人技を極める木目込人形(柿沼人形)

桃の節句にはお雛様、子どもの日には五月人形を飾り、子ども達の幸せを祈るのは日本の美しい伝統行事だ。人形の種類は様々だが、その一つに木目込(きめこみ)人形がある。今回は木目込人形の製作をしている株式会社柿沼人形の工房で、3代目である柿沼利光さんにお話を伺った。(取材・文 宗像陽子 / 撮影 金田邦男)

【プロフィール】
柿沼利光
1979年生まれ。株式会社柿沼人形常務取締役。
経済産業大臣認定の伝統工芸士。
柿沼人形HP:https://www.kakinuma-ningyo.com/
さまざまな表情をもつ木目込人形
長く、日本人には親しまれている木目込人形だが、現在東京都雛人形工業組合の中で江戸木目込部会に所属しているのは5社のみ。そのうちの一つが、1950年に創業の株式会社柿沼人形である。
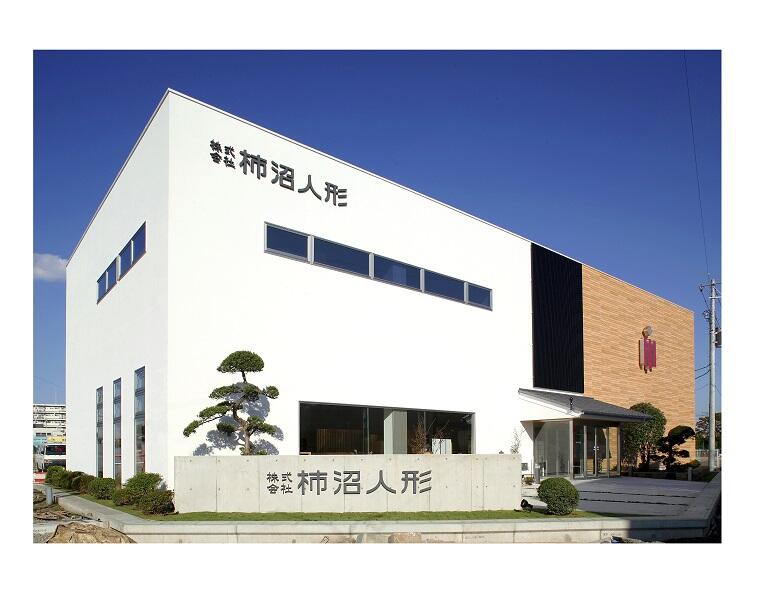

取材をした7月初旬、埼玉県越谷市にある柿沼人形の工房では、小売店向けに展示会が行われていた。五月人形の販売が終われば、新作を作って翌年用の準備をする。この時期に人形屋さんや小売店向けに注文を取り、年内までに納入するというのが年間のスケジュールだ。1階の展示スペースいっぱいに並んだ人形は、それぞれとても個性的だ。今風の、目がぱっちりした人形もあれば昔ながらの切れ長の目のもの、コンパクトに収納箱に収められるもの、小さいながらも三人官女や五人囃子までついているもの、すっきりとスマートなたたずまいのもの、お雛様とお内裏様がそっと寄り添ってポーズをとっているものもある。

木目込人形といえば丸みを帯びたフォルムややさしい表情を思い浮かべる人が多いと思うが、思いのほかバリエーションが多くて驚く。
専門家が分業で、手間と時間をかけて作る
木目込人形は、江戸時代に京都で生まれたと言われる。もともとは木で作った土台の人形に筋目を入れ、そこに布を挟み込んで作り上げていた。その後技法は江戸へ流れ、江戸木目込人形として広まった。ただし江戸木目込人形では木の一刀彫ではなく、粘土で原型を作り、型を取って製作していく方法に変わっている。

木目込人形のルーツとされる人形
現在の作り方と異なり、木彫りの人形に直接筋を入れ、そこに布を挟み込んで作られる。
製法が変わり、いくらか量産できるようになってからは、すべて分業で作られるようになった。胴体を抜く、筋を彫る、着せつける、顔を描く(面相師)、髪を植える(結髪師)とそれぞれ専門の職人が行っている。小道具専門に作る小道具屋さんもまた別の専門職の仕事である。
製作の流れを伺った。
まずは、イメージに従って粘土で人形の原型を作る。原型を木枠に入れて、溶かした硫黄を流し、型を取る。この型を「釜」という。

原型は粘土で形づくられる。写真は「兜」の原型。
「釜」に、桐の粉と正麩糊(小麦粉から抽出したでんぷん)を水で混ぜ合わせて固めた「桐塑」を詰め込み、抜き出して乾燥させる。
土台はこうして出来上がる。はみ出している部分(バリ)にやすりをかけたり、欠損している部分の穴埋めなどをして補正する。胡粉に膠を混ぜ合わせたもので、ボディをコーティングして強度を増す。胡粉は、顔料として使われるもので、原料は貝殻である。
その塗りあがったボディに、深さ1~2ミリほどの筋を彫っていく。筋彫(すじぼり)という。衣裳が切り替わるところには全て筋がはいるが、ボディのラインに合わせて筋を彫るというのは熟練の技に他ならない。


筋に糊を埋めて、型紙に合わせて切った布をヘラで押し込んで接着していく。筋に入れる糊は、「寒梅粉」と言って昔から接着剤として使われている。もち米を蒸して乾燥させ、粉にして晒したもので、水で練って使用する。出来上がった人形が壊れたときの修復などにも使われる。


意外なことに、ボディと布を接着しているのは筋彫の部分だけだそう。体の曲線、着物の袖などカーブのついたところを這うように着せつけるのも熟練の技だ。着物を木目込んだ後、商品によっては手書きで胡粉を盛り上げて模様の輪郭を描き、純金箔を乗せ、内側に彩色を施す。
並行して面相師は人形の頭を作り、顔を描く。結髪師が毛を植え、ボディに取り付ける
多くの人の手によりながら、完成するまでのべ大体1ヵ月くらいはかかっているという。


こだわりの伝統工芸と求められるものの間で苦悩する
利光さんは、原型作りや衣裳の選択、トータルコーディネートに携わる。
翌年の製品は企画会議を経てテーマを決める。それに対してさらに詳細な落とし込み、付随する衣裳、生地、木工屋に対しての依頼をし、最終的なセッティングを行う。人形と台を合わせてみて、すぐに形が決まるわけではない。背景の屏風、脇に配置する雪洞、燭台、花、前道具など金額に合わせて調整しながらセッティングをしていく。

衣裳の布の配分は、利光さんが布を重ねて雰囲気を見ながら決めている。
「十二単をイメージしてもらえればわかると思いますが、襟から出ている色は、当然袖や裾からも出ます。赤が主張しすぎていないか、その下に何色を入れるか。色によって全く違う印象になるので、考えながら色合わせをしていきます」
こうして決められた布を型紙通りに裁断をして、木目込んでいく。


もうひとつ、利光さんには、職人と異業種のデザイナーなどとの懸け橋となる総合プロデューサーとしての役割がある。
展示会場に、さまざまな顔の人形があったのは、それぞれ顔を作る職人が違うから。父親である柿沼東光氏などが作る人形は、書き目といって面相師が一筆一筆、気持ちをこめて描いている。一方で、現代風のぱっちりした目は、樹脂製の目をあらかじめ土台に埋め込み、石膏を掘り出すとその下に目が出てくるような形で作られている。

面相師が一筆一筆目や眉を書き込むのが伝統的な手法
「昔ながらのものを残していきたいので、極力、墨でスッと描いた書き目のものも入れるようにしているんですが、最近は、ぱっちりとした目のものが人気の傾向にあります」
残したい伝統工芸と現代のニーズの匙加減の難しさは、他にもある。
国に「江戸木目込人形」を伝統工芸として認定されているものは、要件が厳しい。製法のほか、原材料も国産の絹織物でなければならないなど指定が細かいのだ。当然、コストは上がる。ニーズには合わない。
広く、多くの人によい伝統工芸品が認知されるためにはどうしたらいいのか、模索は続く。
「伝統は革新の連続である」
柿沼人形では、長年節句人形作り一本に力を入れてきた。しかし、3代目の利光さんは、現状はなかなか厳しいと打ち明ける。
「少子化と核家族化が進み、節句行事も減るという流れが、続いています。実際子どもの数も減って、今年も80万人を下回るということで業界としては、厳しいですね」
そこで、季節ものである雛人形作りとは別に、日常使いできるものを何かできないかと道を探る。節句人形一筋でやってきた祖父や父もそんな動きに反対することはなかった。

「時代に合わせ、先を見すえて新しいものを取り入れるというのがうちのスタイル。うちの会長(父 2代目柿沼東光氏)は、新しいことに対しては肯定的です。『伝統は革新の連続である』という言葉はよく言われました」と利光さん。「おかげ様でうちは、江戸木目込5社の中でも、伝統プラス少し変わったことにチャレンジする会社という立ち位置でして、少々飛んだことをやっても柿沼だからしょうがないとみてもらえるようになっています」と笑う。
こうした機運の中、2015年、商品開発をデザイナーとコラボして行う東京手仕事プロジェクトに参加。作品が採択され、木目込トレイや、木目込招き猫を発表し、海外の展覧会にも出品、注目を浴びた。

パリで行われた「メゾン・エ・オブジェ」2018年9月展で実演する柿沼氏
招き猫自体は昔からあるものだが、柿沼人形の招き猫は、木目込の衣裳に革を使ったり、様々な布がパッチワーク状になっていたり、目の周りにスワロフスキーをあしらうなど、斬新な招き猫を作ったのだ。

実際に見てみると、目の周りにスワロフスキーをちりばめた招き猫は長いまつげも有していて、とてもインパクトがある。このほか当世流行の市松模様、オリンピック仕様、子どもに人気のキャラクターなど、にぎやかな招き猫たちが勢ぞろいしていた。
さらに、台湾人の好きな風水、中国人の好きな金などを取り入れて、バラエティ豊かな招き猫がたくさん生まれた。企業から記念品として配りたいと大量に注文が来ることも多い。
「異業種の人たちとつながると、前を向いて発信をしている方も多くて、面白さと刺激を感じますね」

木目込技術を平面的に用いたトレイも人気だ
歌手の北島三郎さんからは「サブちゃん招き猫」を作ってほしいと頼まれ、最終的には、オリジナルの木目込トレイの注文につながった。ドラマや、バラエティの背景に木目込招き猫が使われることが増えてきた。
「招き猫が福を招いてくれているのかな」。じわじわと柿沼人形にも運がめぐってきたように利光さんは感じている。招き猫以外にも、アマビエ人形などが昨今は人気が出ている。

2年前ほどから台湾の企業とやり取りをして、企業のキャラクターを日本の伝統工芸で表現するという話が、コロナ禍を経てようやく形になりつつある。台湾から中国、そしてさらに海外へという展開に期待が高まる。日本では木目込人形はニッチな産業ではあるが、海外から逆輸入という形で多くの日本人に木目込人形を知ってもらえれば、それはそれで面白いと利光さんは言う。
多くの人が人形を手に取れるのは、平和の証
節句人形は、子どもの健やかな成長を願って、親や祖父母が用意する。招き猫なら、開運招福や商売繁盛といった願いを込めてギフトとしても重宝されている。
「人に対する想いが連鎖してつながるんです。手にする人がみんな幸せになっていただけたらいいかな。こういった商品は、生活や気持ちに余裕がないと買えないもの。たくさんの方が手に取れるということは、世の中が平和ということにもなりますよね」

福を呼び込み、幸を届ける。平和を願い、多くの人が関わって木目込人形は作られている。
ライター:宗像陽子
職人や各種専門家などの取材を多く手掛けている。
オールアバウト歌舞伎ガイド https://allabout.co.jp/gm/gp/1504/
関連記事
タグ一覧