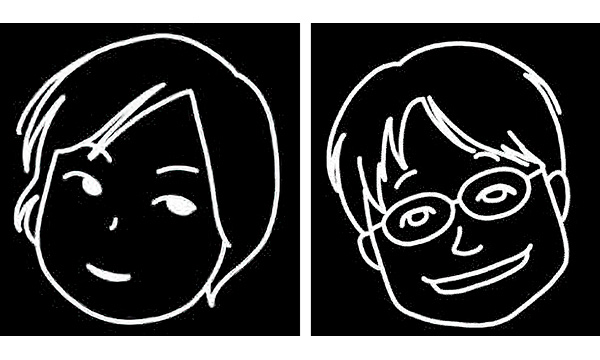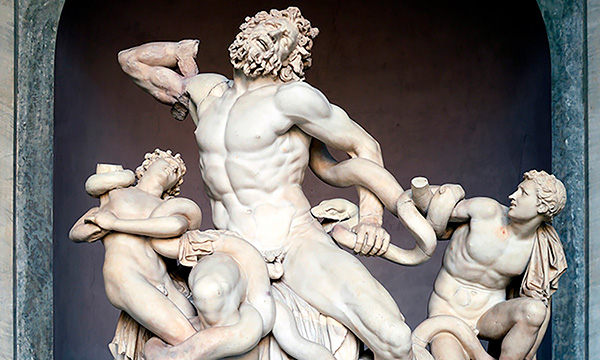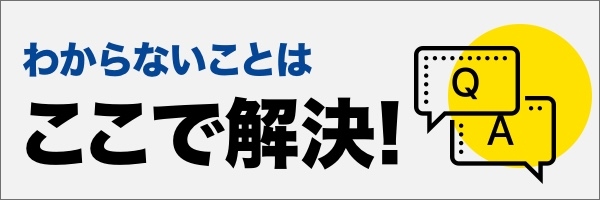✕ 閉じる
建築用
2024年12月26日
都市のなかの人と人を“くっつける”場所や仕掛け(栗生はるか:一般社団法人「せんとうとまち」代表理事、文京建築会ユース代表)

撮影=TADA
栗生はるか(くりゅう・はるか)
一般社団法人「せんとうとまち」代表理事、文京建築会ユース代表。早稲田大学で建築を学び、在学中にヴェネツィア建築大学へ留学。(株)NHKアートを経て、大学で建築教育に携わる。現在、法政大学、慶應義塾大学SFC非常勤講師。法政大学江戸東京研究センター客員研究員として、都市空間とコミュニティについて研究。地域の魅力をさまざまな角度から発信するとともに、銭湯と周辺地域の再生活動を展開している。空き家を活用した地域サロン等も運営中。最近の主な活動に、ワールド・モニュメント財団の支援を受けた「稲荷湯修復再生プロジェクト」や、「国際芸術祭東京ビエンナーレ2020/2021」出展作品の「銭湯山車巡行」がある。
一般社団法人せんとうとまち:https://sento-to-machi.org
文京建築会ユース:https://bunkyoyouth.com/
「ばったり床几」のある光景
私たちの身の回りには、どれほど人と人を“くっつける”場所があるだろうか。かねてより興味があった都市のなかの人と人をくっつける、つまり、出会わせたり、結びつけたりする場所や仕掛けについて紹介したいと思う。
学生時代、全国の「ばったり床几(しょうぎ)」を調べた。「ばったり床几」とは、京都の町屋などの軒先につくられた建具の一種で、跳ね上がった状態のそれを、片手で引き出すと足が振り下ろされ、仮設の縁側となる仕掛けだ。京都ではそれが見世(店)の商品展示棚になったり、祇園祭の見物のための縁台となったりする。「ばったり床几」は京都での通称で、揚見世(あげみせ)とも呼ばれる。地域によって呼ばれ方は異なり、福井県小浜市では「がったり」、徳島の海岸沿いや島へ行けば「ぶっちょうづくり」などとも呼ばれている。徳島の漁村では、跳ね上げると上部の建具としっかりと噛み合い、雨戸の役割も担う。それらは主に、網具などの手入れをする、半屋外の場所として発達したとみられる。
ともかく、これを開くと室内が外へ半間ほど拡張され、不思議な空間が生まれる。そこに家の人がちょこんと座ると、通りがかる人は吸い寄せられるように立ち寄ることになる。人と人を結びつける仕掛けだ。私はこれを「可動式床几」と名づけ、日本全国、すべての事例調査を行った。現地を訪れては、それに座って会話をする住人たちの魅力的な光景を興奮しながら観察した。


「可動式床几」を媒介に交流が起こる高知県の漁村(2003年撮影)
筆者撮影
都市空間、銭湯、喫茶店
そのような場所や仕掛けへの興味が高じて、事例を多く発見できそうなイタリアに留学した。一年を通して広場や道などイタリア国内の公共空間の使われ方を見て回り、記録を採った。長い年月引き継がれてきた都市空間は、さまざまな仮設物を用いることで、多様な人々をつなげる場として自在に活用されていた。一方、日本の都市空間には、広場のような日常的に人々が出会える公共空間が少ない。帰国後、日常的に他者との触れ合いが豊富なイタリアでの生活に思いを馳せるなか、偶然「銭湯」に出会った。2011年よりはじめた「文京建築会ユース」の地域活動で、銭湯を取材することになったのだ。
最初は銭湯建築の面白さに魅了されていたが、それらが次々と廃業し、解体される過程で、銭湯を成り立たせてきた人々や、銭湯と持ちつ持たれつの関係にある周辺地域にまで興味は広がっていった。最近は、消えゆく銭湯を周辺のまちとともに応援する、その名も「せんとうとまち」という一般社団法人までつくってしまった。
そんな銭湯は、都市生活のなかで数少ない人と人を結びつける場所のひとつだ。銭湯では生身の人々の交流が日常的に生じている。湯屋(ゆうや)と呼ばれて賑わっていた江戸時代然り、いつの時代も地域コミュニティの拠点になっている。よく会う常連同士が世間話に花を咲かせるのはもちろん、顔見知りとの簡単な挨拶、そのどちらも苦手だという場合でも、ただ居合わせるだけ、気配を感じるだけでも価値がある場所だと思う。
また、最近リサーチをしたなかでは、昔ながらの「喫茶店」もその役割を果たすひとつだ。コーヒー片手に「おはよう」「いってらっしゃい」で始まる朝のお決まりの光景は勿論、朝・昼・晩と食べにくる常連さん。一人ひとりの好みに合わせて裏メニューを用意するマスターや、お客さんの体調に合わせてお粥までつくるママ。人生相談の場になったり、ご近所さんの物々交換の場になったり……。それらは、無駄なものを排除しすぎてしまった都市生活のなかで、人々の息遣いに溢れた結びつきたくなる場所になっている。

地域住人が日常的に顔を合わせる「銭湯」
筆者撮影

昔ながらの「喫茶店」もまた地域住人のコミュニティ拠点となっている
筆者撮影
急速に淘汰されてゆく地域の拠点
最近、とある美粧院(びしょういん)の最期に立ち会った(美粧院とは美容院のかつての呼び方である)。その美粧院は銭湯の向かいにあり、銭湯同様地域のコミュニティ拠点となっていた。そこは毎日のように、髪を切るわけでもない客が頻繁に出入りする。
ある日は、鏡の前に3人の女性が座って鏡越しに店主の女性と世間話をしていた。誰ひとり頭髪の手入れをするわけではなく、ただのおしゃべりだ。また、そこには「ちょっと遠く行ってきたからさー」と、お土産を持ってくるご近所さんや、「お昼まだでしょ」と、毎日お弁当を届けにくるご近所さんもいる。お隣りの高齢男性は、わざわざ家から移動してきて、美粧院の店先のソファーでデイサービスのお迎えを待つ。さらには、「買い物から帰ってきたよ」「税金振り込んできた」「薬飲んだよ」と頻繁に報告に来る住人もいる。「なーに、そんなの私が知ったこっちゃないよ」と突き放しながらも店主の女性は楽しそうだ。皆、この店が開くと、通りがかりにスーッと吸い込まれ溶け込むように“くっつく”。そうした人々にとってここは本当に居心地が良いのだ。
そんな美粧院も、つい先日、綺麗さっぱり解体されてしまった。開店と同時に磁石のように吸い寄せられていた地域の人々は今、日常的に出会う場所を失い、ばらばらの状態になってしまった。銭湯にしろ喫茶店にしろ、床屋や美粧院にしろ、地域の人々を結びつける役割を持つ居心地の良い場所が、都市から急速に淘汰されつつある。

ご近所さんたちの居場所となっていた「美粧院」
筆者撮影
新たな居場所と地域のリアル
そのようななかで、私たちは地域の人々を“結びつける”場所を、2015年あたりから折りに触れてつくっている。
「文京建築会ユース」の活動をきっかけにつくった、築115年を超える根津の長屋を活用した「地域サロン アイソメ」や、印刷業で使われていた空き倉庫を活用した「UPCYCLE SALON 白山倉庫」などは、消えつつある銭湯の代わりになる場所をつくる目的で始めたものだ。また、「一般社団法人せんとうとまち」では、北区の滝野川稲荷湯の隣りに建ち、元従業員用の住まいであった二軒長屋を改修再生し、湯上がりにくつろげる「まちの湯上がり処 稲荷湯長屋」をつくった。
この3つは、関わるメンバーや、その場所の特性によって多少性格は違うが、どれも地域に開いた都市の快適な居場所となっている。

銭湯のような地域の居場所をめざしてつくられた「地域サロン アイソメ」
筆者撮影

解体された地域の銭湯や喫茶店の物品が活用されている「UPCYCLE SALON 白山倉庫」
筆者撮影

銭湯とまちの間のワンクッションとして機能する「まちの湯上がり処 稲荷湯長屋」
筆者撮影
ちなみに「アイソメ」の目の前は、住人主導で歩行者天国を運用できる「遊戯道路」となっており、「アイソメ」は時にこの通りと一体化して使われる。この通り自体も人と人を結びつける“まちのリビング”のような場所である。
2017年「文京建築会ユース」では、このような誰もが使える地域の居場所を、新しい井戸端「ニュー井戸端」と名づけ、文京区内でそうした場所がどれほどあるかリサーチを行った。発見された25件ほどの「ニュー井戸端」は、空き家や再開発前のビルの一角を利用して、たくましく地域に息づいていた。それらは不動産的には貧弱で、短いスパンでなくなることもあるが、移転して再生したり、また新たなものが生まれることもあり、増加傾向にあるように思う。
一方で、まだまだ都市における人と人とを結びつける場所の不足は深刻だ。先の北区滝野川の「稲荷湯長屋」のオープニングの際には、遠く足立区千住の方から高齢の女性が、「稲荷湯長屋」を紹介した新聞記事を握りしめてやってきた。その女性は、「マンションでひとり暮らしをしていて、一日誰とも話さない日もある。先日、同じマンションで孤独死をした老人がいて、いたたまれない。自分の家の近くにもこのような場所をつくってほしい」と、涙を堪えながら訴えてこられた。わかっていたつもりだったが、リアルな訴えを目の当たりにしたショックは大きい。銭湯のようなかつての地域の人々の居場所が急速になくなる一方で、分断され、孤立化していく都市生活者が悲鳴を挙げている。これが私たちの身近な地域のリアルである。
住人とまちの関係性を編み直す“地域の余白”
しかし、このように地域の新たな居場所づくりをする一方で、拭えない違和感もある。集まることや参加すること、人と交流することが目的の場所、誰かにお膳立てされた場所に、私自身があまり積極的になれないのだ。人との出会いはあくまでも自然なかたちで、偶然に起こるものであってほしいと思ってしまう。また、そのような用意された場所は積極性のある人ばかりが集まり、人との交流に消極的な人は取りこぼされがちだ。
他者との関わり方、結びつき方はそれぞれだ。なにもベッタリくっつかなくてもよい。適度な距離感で簡単な挨拶を交わすだけでもいい、場合によっては先に紹介したように、気配を感じるだけでも人や地域の日常とくっついた感じがする。銭湯も、喫茶店や床屋・美粧院などもそうだろう。あくまでも主目的は風呂に入ることであり、コーヒーを飲むことであり、髪を切りにくることである。その副産物として、他者との交流や店主との触れ合いが生まれることが心地よいのだ。
そのため、先に紹介した居場所の数々は、こちらからは最低限のお膳立てしかしていない。管理の手間を省いているとも言えるが、そこでの交流を押しつけることはなく、やりたいことを、地域住民をはじめとしたやりたい人が自由にやってもらうスペース、“地域の余白”として用意している。
「稲荷湯長屋」などはその甲斐もあって、多くの地域の方々が、さまざまなアイデアを持ち込んで、それぞれの創造性を活かして活用され、自走しはじめている。ゆっくりと柔らかく、新住人と旧住人、学生と地域、既存のコミュニティと新しいコミュニティを結びつけ、銭湯と住人たち、銭湯とまちの関係性を、再度編み直すきっかけになっている。
軒下のベンチ、変わり映えのない居場所
ところで、根津の「アイソメ」の前にはオープン当初から軒下にベンチを設置している。廃業した銭湯から貰ってきたものだ。これといって変わり映えのない、座り心地も良いわけでもない、昔のバス停に使われていたようなベンチだ。しかしこれが不思議と人気がある。人々は、散歩や買い物ついでにそこでひと休み、通りがかりの人と喋ったり、居合わせた人とのんびり時間を過ごしている。最近などはベンチの座の取り合いになったり、座り待ちをして並んでいる人を見たこともある。つい先日は、ベンチの横にどこからか持ってこられた椅子が増え、そこにも人が座るようになっていた。皆、吸い寄せられるようにここに座るのだ。
「ばったり床几」もそうであったが、都市のなかで人と人を“くっつける”場所は案外そんなもので良いのかもしれない。

ご近所さんを引き合わせる「アイソメ」前のベンチ
筆者撮影
関連記事
タグ一覧