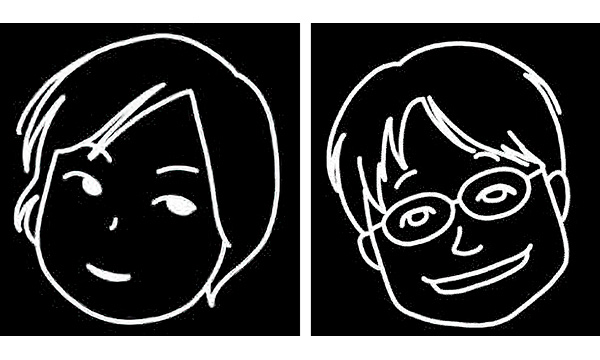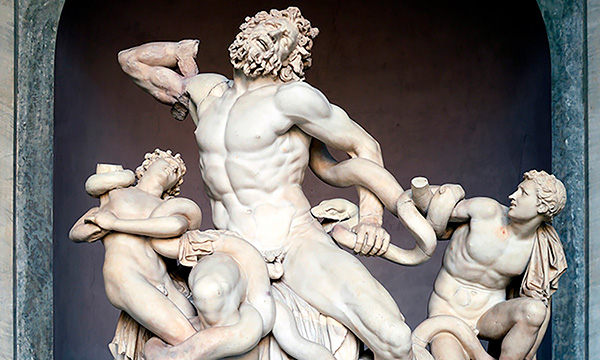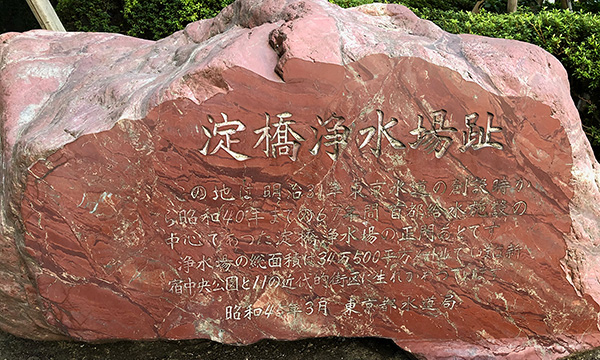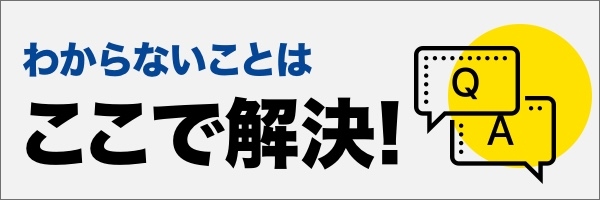✕ 閉じる
建築用
2025年02月21日
世界の手触りを求めて(家成俊勝:建築家、dot architects)

家成俊勝(いえなり・としかつ)
1974年兵庫県生まれ。dot architects共同設立。京都芸術大学教授。主な作品=《馬木キャンプ》(2013)、《美井戸神社》(2014)、《千鳥文化》(2017)、《タイニーハウス 「三角庵」》(2017)、《No.7》(2018)、《仮の家》(2022)など。著書=『山で木を切り舟にして海に乗る』(LIXIL出版、2020)、『POLITICS OF LIVING──生きるための力学』(TOTO出版、2023)など。主な展覧会=「第15回 ヴェネチア・ビエンナーレ 国際建築展」(2016)、「第18回ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展」(2023)、「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ」(2024)など。主な受賞=第2回「小嶋一浩賞」受賞(2021)など。
https://dotarchitects.jp 間接的な世界を繋ぎ合わせていくこと
現在では多くの人々が労働力と賃金を交換することによって生きています。個人の自由が担保されるという意味ではよくできたシステムですが、同時に日々の暮らしはますます間接的なものになっています。私もいろいろな労働をしてきました。振り返ると、夜に倉庫で働いて、その賃金で家賃や食費を払いましたが、倉庫で働くことと、スーパーでネギや白菜を買うことに直接的な関係がありません。貨幣と物やサービスや労働の交換が挟まることでとても間接的な世界に生きているといえます。倉庫での労働そのものには想像力が届いても、ネギや白菜がどこでどうやって育てられて、どういった物流によってスーパーマーケットに並んでいるかは多くの都市生活者にはわからないでしょう。そして暮らしている家に関しても誰がどのように、どのような構造で、どのような素材でできているかなど、わからないことが多いです。
同時にグローバル化により地球のあらゆるところがネットワークされ、あらゆる仕組みがアップデートされ続け、とうていすべてを把握することはできず、このわからなさのなかに煙に巻かれたように暮らしているのが実情です。この間接的な世界のおかげで私たちの日々の暮らしが成り立っていて、それはそれで大切で、そのことによって生きていけるところも大いにありますが、どうすればこの間接的な世界に、直接的な関係をもう少し差し込めるかを考える必要があります。想像力が届く範囲を広げることができるか。自分たちを取り巻く世界を、手触りを持って理解していくことが、私たちを取り巻く環境をよりよくしていくことにつながると思うからです。そのためには、あらゆる専門性や現在の労働環境によって分断された世界を、日々の小さな暮らしを接着剤にして繋ぎ合わせていくことから始めるしかないと思います。制度設計も大切ですが、人口というスケールの大きさを前に個別性や特殊性は失われがちです。
自らつくる自由
私は建築を専門にしていますので、まずはそこから考えていきます。今、日本中に空家がたくさんあります。これらの空家をどうしていくか考えねばなりません。場合によってはひどく傷んでいて住めないと思うことも多いかもしれません。しかし、木造住宅であれば他の鉄骨やコンクリートでできた建物より修復が容易です。構造に関しては専門家に診てもらう必要がありますが、その他の部分に関しては頑張れば自分たちで修繕できる範囲も広いです。
しかし、私たちはいつのまにか自分の家を修繕する力を失ってしまいました。厚生労働省の産業分類を見てみると、設計やデザインの仕事はサービス業に分類されます。このサービスというのは、本来自分でできるものを他の人に頼むことで成り立つ職業と考えることができます。つまり、設計やデザインは誰にでも開かれた領分なのです。こう住みたい、あのような暮らしがしたいからこのような家にしたいなど、構想をめぐらすことができますし、実際にある程度つくることも可能です。その時に、こうあるべきとか、これが普通であるといった通念を前提にせずにいかにこれからの生き方や暮らし方を考えることができるかが大切です。タワーマンションの上層階に住むことをひとつの目標にするなんてことは、消費が美徳であった前世紀の代物です。専門家の設計にしても至れり尽くせりで、住み手の現時点での要望をなんとかすべて飲み込んで設計することや、狭い意味でのデザインに囚われることが逆に住み手が本来持っている自らつくるという自由を奪っているとも言えます。
日本でも他の国でも、廃屋となった工場や学校を仲間たちと力を合わせて地域やその仲間たちの活動や交流の場所として使用しているように、打ち捨てられた建物を、かつての用途とは違うかたちで、専門家が入らずとも上手く活用している事例は多くあります。それらの活動を見ていると、誰かに丸ごと頼まなくても自分たちでできる世界が広がっていることがわかります。そのためには、基本的な材料、工具、その組み合わせ方を、実践を通して理解していく必要があります。
私たちの事務所では、非専門家の人たちにそのような技術や知識を知ってもらうジムを開こうと考えていますが、ここで問題になるのが、月曜日から金曜日まで働いていて、残業や土日も働かなくてはいけない時もあるのに、そのような時間がないということです。とある地域の消防団の方にお話を聞いた際も、かつては農業や自営業を営む人が多く、訓練に多くの人が参加できていたが、今は会社員が多く、時間の融通が利かないために消防団に入る人がとても少ないという内容でした。町内会の会合に参加することができない人も多くいるでしょう。現在、私たちの事務所が少しお手伝いさせていただいている畑についても、専業農家、兼業農家、会社員と、世代を経て生業が変わることで耕作放棄地が増えています。現在の労働のあり方が、地域やコミュニティ、自分たちでつくることが大切と言っても結局はなかなか貢献できない状況にさせているのです。
専門分野を越え、領分を増やしていくこと
今のシステムでは、人口減少によって労働力が確実に足りないため、国策として労働市場にどんどん人を送り込むことになっていますが、それだけが果たして豊かな生き方と言えるのでしょうか。賃金が5%上がることも大切ですが、もっと大切なことがあるとも思います。私たちは賃金と引き換えに、自らつくりだしたり、誰かのことをもっと大切にしたりという機会を手放し続けているのではないでしょうか。急に変化させることは無理ですが、ジワリジワリと、自分たちで考え、つくり、使っていく領分を増やしていかなければいけません。そこでの喜びや苦しみを経験しなければいけないと感じています。そのために、これからは専門性に閉じず、日々の暮らしのベースを問い直して、その生活に紐付くあらゆる領域をひっつけていくことが必要です。それは1人でできることではなく、共感する仲間が必要です。私は建築の設計やつくることと合わせて、自分の専門分野を越えて、領分を増やしていくために、小さな倉庫を改修するワイナリーの設計と合わせて、ぶどう畑のお手伝いと、耕作放棄地で畑をはじめる予定です。建築だけを考えるととても小さいスケールですが、畑というフィールドを含めると大きなスケールです。地球という大地の一部分を触っている感触があります。まだまだ先に想像力が届いていきそうです。

撮影=Kazuki Yamashita

撮影=Kazuki Yamashita

ワイナリーに利用する元堆肥舎(筆者提供)

ワイナリーに利用する元牛舎と元堆肥舎(筆者提供)
関連記事
タグ一覧