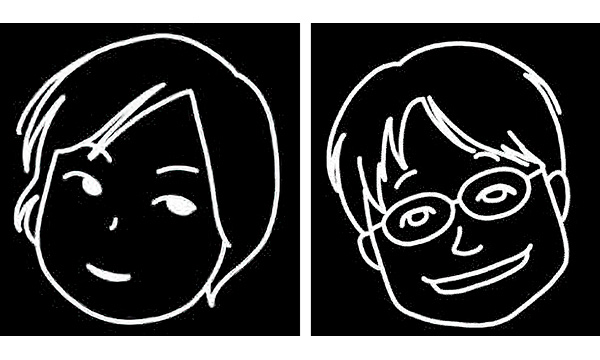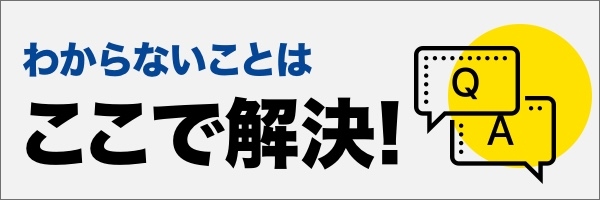✕ 閉じる
建築用
2022年02月18日
まちの「のりしろ」を考える(大野暁彦:ランドスケープアーキテクト)
大野暁彦(おおの・あきひこ)
1984生まれ。株式会社SfG landscape architects主宰。登録ランドスケープアーキテクト、自然再生士。名古屋市立大学准教授。《新代田ポケットナーセリー》(2016)、《太田市美術館・図書館》(2018)、《ぶるーむの風》(2019)、《鍋屋バイテック会社広場》(2020)ほか。

撮影=田中源
ランドスケープアーキテクチャの歴史にまず登場するのが、フレデリック・ロー・オルムステッド(1822〜1903)らが設計したニューヨークのセントラルパークである。グリッド状に計画されたマンハッタン島の真ん中に、大きな四角い余白が公園として計画された。
この功績はコレラが流行していた当時においても大きかったが、新型コロナウィルス感染症が流行するなかでもセントラルパーク内に野営病院が設置されるなど、この公園が大都市に存在する意義を示している。日本でもPCR検査場として公園が使われている事例もみられるように、公園のフレキシビリティの高さを示している。
こうした事例が示すように普段何気なくある公園が、都市のなかで発生するさまざまなハプニングをなんでも受け入れる場所として機能しており、都市を支える重要な基盤であると気付かされる。
公園はランドスケープアーキテクトの仕事の一部にすぎないが、その他の多くの仕事でも「のりしろ」を考えることが多い。バラバラになっている要素同士をつなぐ仕事だ。
「のりしろ」にあたる「余白」は、何もないところと捉えることもできるかもしれないが、むしろ何もないからこそ、さまざまな場所、人、自然とをつなぐものになる。

にぎわう南池袋公園(筆者撮影)
江戸のまちに組み込まれた「余白」としての庭

参謀本部陸軍部測量局の地図に見られる庭と池
引用出典=参謀本部陸軍部測量局五千分一東京図測量原図
江戸時代のまちの様子は、明治10年代に参謀本部陸軍部測量局が測量した地図からおおよそ知ることができる。その地図を見ると池が多いことがわかる。さらによく見るとその多くは屋敷や寺社に付随する庭の中にあることがわかる。
参謀本部陸軍部測量局作成の地図全範囲で1,300以上の池が確認でき、その多くは沖積低地部か武蔵野台地と沖積低地部の境界にあたる崖線沿いにある。これらの池は、崖線沿いからの湧水や河川や運河、海などの水を引き込んでおり、江戸の水系の一部となっていた※1。
江戸のまちの半分近くが低地に立地するなかで、こうした池は生活用水の一部となり、洪水調整機能を果たし、一部では舟運機能も果たしているなど、重要な都市機能の一部を担っていた。
また、庭園のある武家屋敷のほとんどは下屋敷であり、もてなしの場としてこうした池のある庭が使われていたと考えられる。
このように江戸のまちに組み込まれた庭園は、余白として江戸の都市機能を支えていたことがわかる。
現在までに、こうした都市に組み込まれた余白はほとんどが失われ、十数カ所の庭園のみ現存する。また、浜離宮恩賜庭園など一部の庭園以外は、水系との接続も絶たれてしまっている。
それでも、崖線沿いの庭園である新江戸川公園(肥後細川庭園)や甘泉園(清水家下屋敷)などに行くと、東京のもつ高低差を活かした大きな池のあるダイナミックな風景に感動するだろう。
建物が立ち並ぶ現在ではほとんど感じることのない、東京の地形構造や水脈に気付かされる。
![]()
公園と庭園
江戸時代に江戸東京につくられた庭園の大部分は消失してしまい、残された庭園も多くは公園となった。余白として都市に残されることとなったが、庭園であった時のような生き生きとした風景ではなくなってしまった。
それは、単純に言えば持ち主が変わってしまったからである。六義園ひとつとっても各時代におけるその庭園の様相は異なり、庭園主によって大きく異なっていたようであり、荒廃していた時代もあったようだ※2。こうした変化は、時代性や社会性も影響していたとも考えられ、常に庭園の風景は変化しうるものであるとわかる。
中国の世界遺産のひとつ、蘇州でも「保存された」庭園群を見ることができるが、驚くことに毎日のように地域住民が利用している姿がある。近所の人と大声でおしゃべりをしながらナッツを食べて、その殻をそこらへんに撒き散らしていた。
日本の文化財庭園のような仰々しさはなく、生活感のある空間であると感じた。韓国の庭園を調査した時も庭園の中のひとつの東屋でバーベキューをしている家族に出会ったことがあった。文化財庭園に対する見方の違いでもあるが、庭園空間が今も生きているなと感じる。

中国・蘇州の世界遺産庭園の中にある日常風景(筆者撮影)
計画するが設計しない
自然と人や都市との関係を考えるうえでも「のりしろ」となる余白は大事である。
自然が豊かな環境は、見通しも悪く蚊をはじめとしたさまざまな昆虫や動物などもおり、人間が快適に過ごせる環境でないことが多い。
一方、植栽や土、水の少ない都市では生物の生息環境としては不十分である。人も自然もうまく共存するためには、中間領域が必要になる。
里山のように人にとっても自然にとっても過ごしやすい環境を構築するためには、人のための空間であっても生き物が介入できる余地があることが大事である。

《ぶるーむの風》全景(筆者撮影)
私が以前関わった仕事のひとつに《ぶるーむの風》(2019)というプロジェクトがある。
障がいをもつこどもたちのための支援施設に隣接する庭を設計するプロジェクであった。敷地には、計画前から雑木林があった。雑木林も人の手で植栽されたものであるが、周辺の宅地化が進むなかではこうした緑地は貴重である。従前はボーイスカウトの活動で森全体が使われていたようで、土が踏み固められ大きな木以外は笹がいくらか生えている程度であった。

地面が踏み固められ、大きな木以外は植物がほとんど生えていなかった計画前の雑木林(筆者撮影)
施設の計画にあたってボーイスカウトの活動場所ではなくなることから、土だらけであった地面に新たに植栽し、生き物のための空間とし、人は園路など限定された場所のみ入れるようにしている。
私がここで計画時に決めたのは舗装の外形線であり、それは人と生き物双方の共存を目指すために考えた線である。その線によって生まれたそれぞれの空間はあえて作り込んでいない。地形形状はほとんど改変していないので、舗装したところは地形形状によって、多様な領域を形成している。
一方の生き物へ明け渡した領域は、もともとの森の端部に少しだけ残っていた植栽と表土をセットで移植している。表土には、その時には現れていなくてもさまざまな種子を含む。そのため、しばらくすると思わぬ樹種が土から顔を出し、
もともと移植した時には数種類程度であった植栽は竣工してからどんどん増えて十数種類以上にまでなった。舗装もこの植栽も、余白として計画したが、設計したものではない。

《ぶるーむの⾵》の園路と植栽(筆者撮影)
接着剤の役割
建築家やプロダクトデザイナーからすれば、設計をしないことは半ば職能を放棄したとも捉えられるかもしれないが、そうではない。
ランドスケープアーキテクトは単独でプロジェクトを実施することもあるが、住宅やビルなど建築をともなう仕事では建築家と協働することが多い。そのなかでは、私は接着剤になれるように関わっている。
物理的なことでいえば、建築本体と敷地との間の「つなぎ」を考えることである。
その「つなぎ」は単に建築と周辺との間を埋めるだけでは建築のもつ魅力、周辺のまちや自然のもつ魅力を台無しにしてしまう。それぞれの魅力を理解し、現状以上にその魅力を引き出すことが必要だと考えている。
単に「すき間を埋めるもの」や「くっつけるもの」ではだめで、それぞれがより良く見えるようにふるまうべきである。
また、私が活動のなかでつなごうとしている相手は、人であれ生き物であれ、その反応は予測できることもあればそうでないこともある。つなげたいと思っているものを強く固くつなぎ合わせるのではなく、つなぐものそれぞれが予測を超えた挙動を起こすことを許容できる、寛容な「糊」をデザインできるとよいのではと考えている。
【了】
※1──拙論「池泉形態からみる都市環境と庭園意匠の相互関係に関する研究」(千葉大学学位論文、2014)
※2──小野佐和子『六義園の庭暮らし──柳沢信鴻『宴遊日記』の世界』(平凡社、2017)
関連記事
タグ一覧