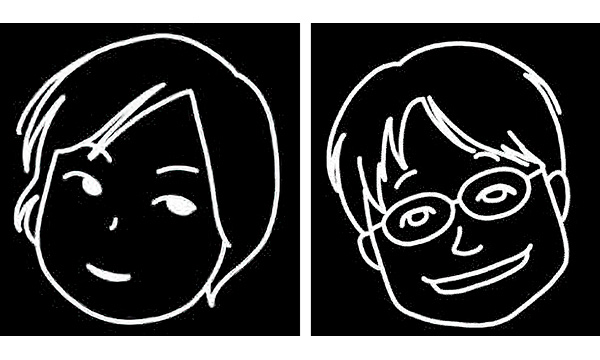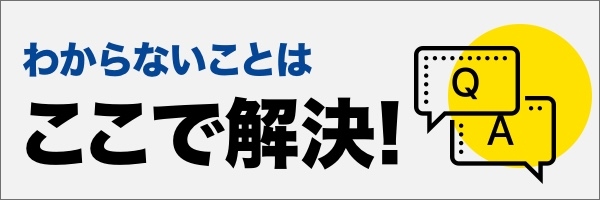✕ 閉じる
建築用
2023年10月24日
差異と類似を発見するためのペアリング──協働がもたらすつくることの自由さと楽しさ (西澤徹夫:建築家)

©Maetani Kai
西澤徹夫(にしざわ・てつお)
1974年生まれ。建築家。西澤徹夫建築事務所代表。京都工芸繊維大学特任教授。
主な建築作品
《東京国立近代美術館所蔵品ギャラリーリニューアル》(共同設計=永山紀子、2012)、《長良の場合》(2015)、《西宮の場合》(共同設計=酒井真樹+安藤僚子、2016)、《京都市京セラ美術館》(共同設計=青木淳建築計画事務所、2019)、《八戸市美術館》(共同設計=浅子佳英+森純平、2021)、《熊本市現代美術館リニューアル》(2022)ほか。
展覧会会場構成
「パウル・クレー──おわらないアトリエ」展(2011)、「映画をめぐる美術──マルセル・ブロータースから始める」展(2014)、「Re: play 1972/2015——『映像表現’72』展、再演」展(2015)、「恩地孝四郎」展(協働=町田恵、2016)、「アジアにめざめたら──アートが変わる、世界が変わる 1960–1990年代」展(2018)、「あるがままのアート──人知れず表現し続けるものたち」展(2020)、「ギフト、ギフト、」展(2021)、「森村泰昌──ワタシの迷宮劇場」展(2022)、「深瀬昌久1961–1991 レトロスペクティブ」展(2023)ほか。
変わりうるけれども変わっていないように見えるもの
複数のものを一定間隔で並べると、ある秩序が生まれます。これがいちばん原始的な構造だと思います。このとき、一つひとつの要素は、物理的にも化学的にも、必ずしもくっついている必要はありません。並びがつくりだす構造が、それぞれの要素をくっつけていることになるからです。一方で、このうちのいくつかの要素の場所を入れ替えたらどうでしょうか。あるいは、どれかを並びから取り外してみたり、まったく別の要素を端に足してみたらどうでしょうか。やはりこの原始的な構造は維持されているように思えます。複数の要素がつくりだすこの関係性には終わりがなく、つねに変わりうるけれども変わっていないように見える、という性質があります。僕が建築でつくりたいものは、端的に言えばこういうものなのではないか、と考えています。
専門性を持ち寄ることによって得られる自由さ
建築は機能や構造、法律といった多くの条件、材料や色やテクスチャーといった審美的基準、クライアントや施工者や協働者といった関係者など、じつにさまざまな要素から成っています。さらに、実際に使われ始めてからの出来事や加えられていく家具や活動する人々にも想像を広げてみれば、ひとつの建物が巻き込む物事の多さと多様さはじつに膨大で、どこまでがその建築に関わっているといえるかを把握することは容易ではありません。
そのような膨大な広がりをもつ現象全体を建築の創造行為と捉えた場合、ではそれを設計するとはいかなる方法で可能なのでしょうか。これはじつはとても今日的な問題です。なぜなら、なにかとても生き生きとした現象をつくりだしているのは建築家だけではないということ、どこまでが建築かは見る人や使う人によって異なるということは現代では自明だからです。にもかかわらず「つくる」ということにはそもそもどういう方法が可能なのか。
僕が取り組んでいる試みのひとつはほかの建築家との協働です。これまで実作としては永山紀子さん、酒井真樹さん、安藤僚子さん、町田恵さん、青木淳さん、浅子佳英さん、森純平さん、板坂留五さん、工藤浩平さん、コンペでも榮家志保さん、亀田康全さん、乾久美子さん、畝森泰行さん、岩瀬諒子さん、小黒由美さん、といった多くの建築家と組んできました。とくに規模の大きな、つまり全体性がとめどなく広がっていくようなプロジェクトでは意識的に協働してきたと思います。
建築物には必ず工期があり予算があり確認申請の範囲においてひとつのまとまりがありますが、それをひとりの建築家が自らの作家性のもとに統合していくには無理があるのではないか、と感じてきました。同時にそれはひとりの建築家のステートメントでひとつの建築が説明されてしまうことへの違和感であり、またたくさんの説明の切り口が用意されていたほうが建築が自由になるのではないか、という期待感なのだろうと思います。
協働者がそれぞれの専門性を持ち寄ることによって、互いが気づかなかったことに気づくこと、あるいは交錯した議論が脱線することで迂回した思考の領域がプロジェクトに深みを与えることの実感はたしかにあります。例えば《八戸市美術館》(2021)の設計では、浅子さんから、商業建築での豊富な経験に基づく物品の搬入搬出時の扱いの煩雑さについての指摘がそのまま新しい美術館の運用のためのディテールに活かされるということがあったし、新しい時代のジェンダーレストイレの検討に際しては浅子さんによる数年にわたるリサーチが活かされました。同じく森さんからはアーティストの視点に立っての作品のインストール方法や制作環境についての指摘を設計に反映することができました。2人の共同設計者の専門分野について言われれば理解できるものの、それ自体をそれほど中心的関心に置いていなかった僕としてはとても新鮮なことでした。

《八戸市美術館》(2021)外観
©八戸市美術館
発見していないものを発見するためにある協働者
この原稿を書いているのは、TOTOギャラリー・間での「西澤徹夫 偶然は用意のあるところに」展(会期=2023年9月14日–11月26日)の準備の真っ最中です。
この展覧会では、これまで関わってきたプロジェクトの建築模型を建築物や展覧会会場構成の部分を示す断片として扱い、かつ、異なる2つのプロジェクトをペアで並べることで、ひとつのステートメントとして説明することを避けるためのプレゼンテーションを試みています。
例えば、《西宮の場合》(2016)という住宅について、いろいろと解説したいことがあるところをぐっと抑えて、住宅がスロープで街と繋がっているという点にだけ注目してみると、機能も規模もまったく関係のない《京都市京セラ美術館》(2019)の本館と前面道路もスロープで接続している、という形質的な類似点だけが浮かび上がってきます。あるいは、《907号室の場合》(2015)というマンションの1室の改修でクライアントが所有する大量の物をどう扱うかが設計の出発点になったことと、《八戸市美術館》(2021)で学びを活動の中心に据えた新しい美術館で使う道具や什器のあり方を考えていたことがとても似ているのではないかと思い当たった、ということがありました。一方同じ《八戸市美術館》でも、個室群と呼ばれる小さな部屋の連続的な機能配置を提案したことは、《東京国立近代美術館所蔵品ギャラリーリニューアル》(2012)で担当学芸員から最初にオーダーされた全体を小部屋化することと通底しているのではないかと気づいた、ということがあります。あるいは、アーティストの竹浪音羽さんに描いていただいた《八戸市美術館》の絵が示す彼女の視点と、「映画をめぐる美術──マルセル・ブロータースから始める」展(東京国立近代美術館、2014)の会場構成は部分と全体がつねに連関して想像できる表現方法がシンクロしていることに気が付きます。


「西澤徹夫 偶然は用意のあるところに」展(会場=TOTOギャラリー・間、会期=2023年9月14日–11月26日)での展覧会準備のようす
©西澤徹夫建築事務所

《八戸市美術館》開館1周年記念イベントのようす
奥には個室群が並んでいる
©八戸市美術館

《東京国立近代美術館所蔵品ギャラリーリニューアル》(2012)
《八戸市美術館》と共通する連続した小部屋
©富井雄太郎
こうして任意の2つをくっつけて並べてみると、じつはプロジェクトをまたがって、確定的ではないものの、興味や関心、あるいは仮説のようなもののまわりをぐるぐると巡りながら設計活動を行なっているのではないかと気付くことになります。
そしてじつは、個別のプロジェクトの内部で取り組むべきことの外部に、いくつもの伏流するテーマが、自分の設計する内容をくっつけていることに思い当たるのです。ここで重要なことは、この組み合わせは「西澤徹夫 偶然は用意のあるところに」展でプレゼンテーションするペアにとどまらず、自作と、影響を受けた作品や好きな作品の組み合わせにまで広がって、おそらくいくらでもつくりだすことが可能であることです。複数のまったく文脈を異にするものをくっつけてみると必ずそこには差異と類似が事後的に発見される、という概念的な働きを前提に考えてみると、どんなものでも一旦くっつけてみることは、世界をより有機的に理解したり発見したりすることに役立つのかもしれません。そこには世界を、自分を、より多角的に解釈し直し続けることの自由さと楽しさがあるように思います。ですから協働設計者の存在は僕にとって、まだ発見していないものを発見するための、戦略的なペアリングなのだと、いまのところは考えています。
関連記事
タグ一覧