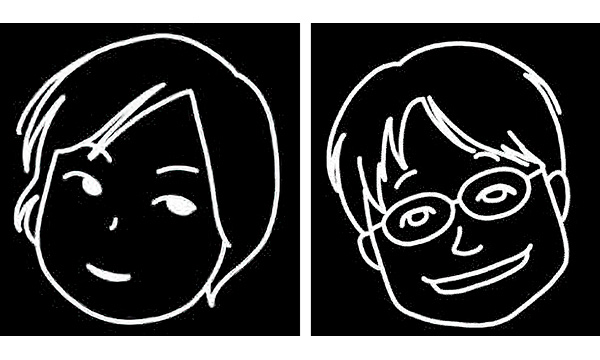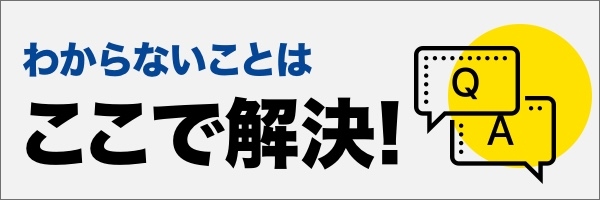✕ 閉じる
建築用
2022年11月01日
くっつけるのか、くっつけないのか。それが問題だ。 ──コンテナ建築との20年(吉村靖孝:建築家)

吉村靖孝
1972年生まれ。建築家。早稲田大学教授。吉村靖孝建築設計事務所代表。主な建築作品=《Nowhere but Sajima》(2008)、《中川政七商店新社屋》(2010)、《Red Light Yokohama》(2010)、《TBWA/HAKUHODO》(2012)、《Window House》(2014)、《フクマスベース》(2016)ほか。主な著書=『超合法建築図鑑』(彰国社、2006)、『EX-CONTAINER』(グラフィック社、2008)、『ビヘイヴィアとプロトコル』(LIXIL出版、2012)ほか。
https://www.yasutakayoshimura.com/
菊竹清訓氏とドライジョイント
生前の菊竹清訓氏(建築家、1928〜2011)にお目にかかる機会をいただき事務所を訪ねたことがある。
インタビューの本題はまったく別の話だったので期せずしてと言わざるをえないが、たまたま庭先に無造作に転がっていた鉄の塊が、1970年に行なわれた大阪万博のランドマークのひとつとしてつくられた《エキスポタワー》(菊竹清訓、1970)のボールジョイントであり、それが溶接を使わないドライジョイントとしてデザインされていて、いつでも容易に取り付け/取り外し可能であったことを直接うかがったことがよい思い出である。
たしかに、生物が新陳代謝するかのように環境や状況に応じ変化していくことが目指されたメタボリズム建築のなかには、その思想的背景とは裏腹に溶接やコンクリートで固められ取り外すことができないものもある。氏の立場からすれば、「取り替え」られずになにが代謝か、ということになるわけだ。
当時すでに万博から40年近く経過していたはずだが、まるで昨日のことのように語気を強められたのには、正直面食らった。しかしそれ以降、私がドライジョイント信者になったことは言うまでもない。
海運コンテナの建築的可能性の発見
2001年の夏、2年間住んだオランダから帰国し、その直後に「30✕100 MATERIAL──マテリアルの使い方」展(会場=東京電力技術開発センター、会期=2001年9月29日〜10月8日)に参加して、初めて海運コンテナを「材料」にしてつくる建築の提案をして以来、私はコンテナ規格を流用した建築と、付かず離れずの距離を保ちながら20年以上の付き合いをしてきた。
2008年には『EX-CONTAINER』(グラフィック社)という本を書いて国内外のコンテナ建築を紹介した。本になるということは、世の中にはすでに十分な量の実例があったということだ。
新しもの好きの建築家がなぜ前例豊富なコンテナ建築に興味をもつのか、読者のなかには不思議に思う人もいるかもしれない。しかし私を惹きつけた課題が2つあって、ひとつは、日本の場合、ISO(国際標準化機構)規格の海運コンテナそのままではJIS(日本産業規格)を要求される建築の主要構造部として使うことができず、そこに工夫の余地があったことである。アメリカなどでは、対中国の輸入過多が続いて空のコンテナを送り返すわけにもいかず、行き場のないコンテナを大量に余らせていたことが社会問題化し、コンテナのリユースが喫緊の課題だったわけだが、日本では、リサイクルやアップサイクルよりも、一からデザインし直した新造コンテナで、法の規制を乗り超えることのほうが挑戦しがいのあるテーマだったのである。
もうひとつの動機としては、先行事例のなかにコンテナ同士を現場で溶接してしまい、コンテナ建築が本来備えている移動可能性を活かしきれていないものが少なくなかったことが挙げられる。ユニット同士の接合をドライジョイントとして、完全にはくっつけず、集合すれば建築になり、組み合わせを変えれば別の形になって、また分散してリサイクルすることもできる。そんな建築をつくってみたいと素朴に思ったのだ。
流通インフラとしてのコンテナからコンテナ建築へ
さて、コンテナそのものにも簡単に触れておきたい。1963年にISOの海運コンテナ規格が定まってから地球上のあらゆる地域へと積み荷を荷解きせずに運ぶことが可能となり、世界的にコンテナの取扱量が急増し、それに伴い輸送船も大型化して、巨大コンテナ港を生んだ。
たとえば、私が住んでいたロッテルダムは言わずと知れた世界有数の港街であるが、その始まりは、13世紀にロッテ川とマース川の合流地点につくられた海水の流入を防ぐための小さな堤防(ダム)である。2つの川を行き来するためには堤防を越えなえればならず、そのためには荷の積み替えが必要になって、人が集まり、街ができた。その後植民地との貿易拠点となり、産業革命を経て、20世紀にはコンテナ船の大型化に柔軟に対応するために港の拡張が繰り返し行なわれ、ヨーロッパ最大の港へと急成長した。言うなれば、ロッテルダムこそ、コンテナによって激変した都市で、そこに暮らし毎日コンテナを眺めていたことが、後の私に影響したことは疑う余地もない。
世界に目を向けても、いまやコンテナによる輸送は、グローバル化した消費社会を支える大事なインフラであり、錆びたコンテナがまるで血流のように日々世界を駆け巡っている。この流通網をハックすれば、建材を輸入するだけでなく、海外で建築をつくり、建築ごと輸入することも可能になるし、できあがった空間をまた別の場所へと移動することもできる。それがコンテナ建築の可能性であり、だからこそドライジョイントにこだわりたいのだ。
空間としてのコンテナはどうだろう。コンテナの取扱量を表わす単位TEU(Twenty-foot Equivalent Units)にもなった20ftコンテナの外形はおよそ、(w)2.4 m ✕(d)6 m ✕ (h)2.6 mで、内装を施すとちょうどル・コルビュジエが設計した《ラ・トゥーレット修道院》(1960)の僧坊と同程度の大きさになる。余分なものを削ぎ落とした修道院での暮らしを支える生活最小単位とコンテナの寸法が図らずも一致しているわけだ。生活の単位でもあり、輸送の単位でもある、コンテナのこの単位空間としての優秀さもまた、私の欲望を喚起するひとつの要因だろう。
コンテナ建築とドライジョイントの課題
一方で、建築にするには課題も多い。耐久性やコストパフォーマンスの面などから海上コンテナは鉄製のものが主流であるが、外壁としてみた場合、構造と外壁が一体化していることは便利な反面、温熱負荷や熱橋などを考えると明らかにマイナスである。
それから精度の維持にも課題がある。通常の鉄骨工事では仮締めをして精度を出してから固定し、仕上げをしていくが、コンテナはそれができない。先に工場で仕上げまで施工できてしまうことは精度を上げるうえで理にかなっているはずだが、それをしてしまうと現場で融通が利かない。ほんのわずかな製造誤差であっても、5つ6つと積み重なると、ボルトが通らないなどの問題が起こる。どうクリアランスを確保するのかは永遠の課題だ。
また、ドライジョイントと口にするのは簡単だが、これもなかなか難しい。2列、2行、2段、合計8個のコンテナをつながなければならないような場合、中央の接合部については、外から手を入れてジョイントすることはできないからだ。この手が入らないという単純な問題も案外根が深い。
メタボリズム建築として構想され、ひとつのカプセルを1ユニットの居室空間とし、それらカプセルの取り外しや交換が想定された《中銀カプセルタワー》(1972)において、黒川紀章はカプセルの4つのジョイントのうち手が入らない下部の2つをダボとして差し込んだうえでコンクリートで固めたが、これが解体のハードルを上げたと聞く。コンテナ建築においても同様で、ユニット室内側からジョイントできるよう工夫しても、その部分の仕上げはどうしても現場施工になるというジレンマに直面する。
コンテナ建築の実作を通じてこれらの問題をひとつずつケースバイケースで解決してある程度のノウハウをストックしてきたが、まだまだ改善の余地はある。乗りかかった船、どのみちライフワークだと覚悟しているので、興味のある同志を随時募集中である。

ベイサイドマリーナホテル横浜(神奈川県、2008)の施工中の様子
コンテナをコテージ型客室として用いた。仕上げや設備を組み込んだユニットをタイで製造し、海沿いの敷地に設置した。基礎を打っておけば、現場では背面にまとめた設備を接続するだけで完成するという仕組みを考案し工期を短縮するだけでなく輸送費などを含めた建築コストを大幅に下げることが可能になった。(筆者提供)

エクスコンテナ・プロジェクト(東北地方、2011)
東日本大震災後、被災者のための仮設住宅の工事が遅れていると聞き、寄付を募ってコンテナによる仮設住宅の試作品をつくり東北各地を回った。輸送しやすいというコンテナの特徴を活かし、仮設住宅として設置後、避難期間を終えてからも自宅のあった土地に持って帰って増設しながらそのまま住める住宅を目指した。(筆者提供)

GPT TAISHO(大阪府、2020)
コンテナと木造を組み合わせることで狭い敷地でも有効に床面積を確保できる住宅を目指した。ジョイント方法に関する特許取得済み。(筆者提供)

GTH(山梨県、2021〜)
コンテナ同士の接合部の施工の難しさを回避する最良の方法として、1ユニットのみのホテル客室を提案した。狭い室内を水回り中心の「ぬれる部屋」と全面ベッドの「ねれる部屋」に分けた。(筆者提供)
関連記事
タグ一覧